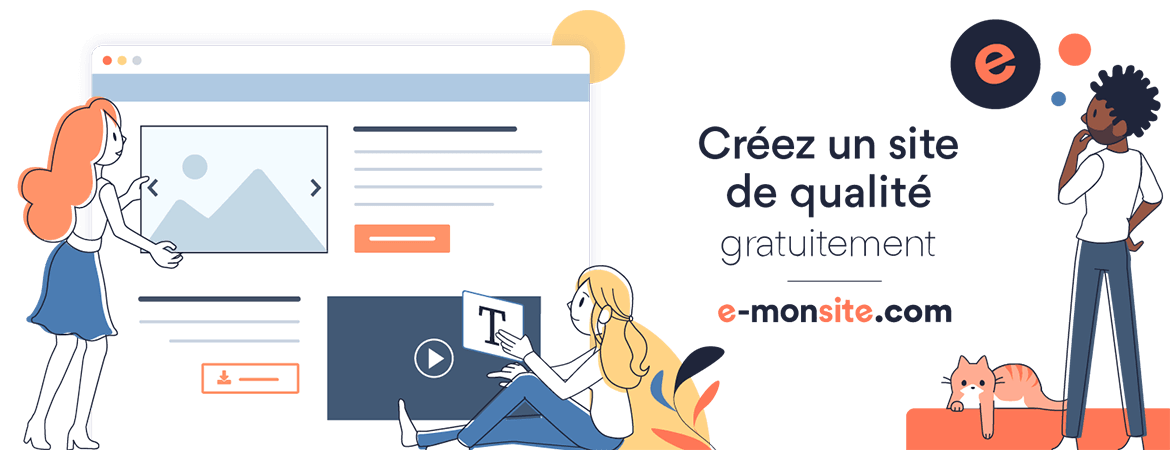を胸元に抱えて厩からでたタイミングで、副長が怒鳴ってきた。
厩のまえで仁王立ちになり、ムダに恰好をつけている。
そのうしろでは、島田と蟻通と俊冬が荷馬車に武器弾薬を積み込み、安富はせっせとお馬さんたちの準備をしている。
なんだよ。だれかもっとはやく起こしてくれればよかったのに。
これじゃぁまるで、t恤品牌 泊りがけの研修会で呑みすぎて寝坊したみたいじゃないか。
「二度、起こしたよ」
俊冬が、弾薬らしきものが入っている木箱を荷馬車に積み込みながらいった。
「兼定兄さんは数えきれないほど、おれが二度、わんこが三度、それぞれ起こした。が、きみは「もうちょっと」と甘えたことをいうだけで、ちっとも目を覚まそうとしなかった」
マジかよ?
全然気がつかなかった。
ってか、数えきれないほどプラス五度も起こされて気がつかないなんてことあるのか?
このおれが?
スマホで目覚ましを設定していても、たいていは鳴ってすぐに起きることができていた。
それこそ、スヌーズ機能をありがたく思ったことなどほとんどない。
そのおれが?
まあ、めっちゃ疲れていることは否めない。
それでも、数えきれないほどとか五度も起こされて気がつかない?
「いいから、はやくいってこい」
「す、すみません」
駆けだそうと副長に背を向けた瞬間、うしろから肩をつかまれた。
「深更のことはだまっていろ。なにもなかった。いいな?」
副長は、そうささやいた。
「承知」
そう応じるしかない。
副長が、なにゆえ俊春のことで俊冬と諍いになったことを、なかったことにするのかはわからない。
その意図は、残念ながらおれにはよむことはできない。
とりあえず、井戸に向かってダッシュした。
厩へと戻ったときには、みんなすでに準備が整って騎乗したり馬車に乗ったりで待ち構えていた。
おれがお馬さんに乗ると、副長が「竹殿」をあゆませはじめた。
野村あらためジョンと市村と田村が見送ってくれた。
野村あらためジョンなどは、めっちゃニヤニヤ笑いながら掌を振っている。
おまえくらいだよ。ちゃんとした隊士なのに一度も戦に参加していないのは。
しかも、死んだことになっているし。
とんでもないやつである。
これが京で新撰組がバリ絶好調のときだったら、切腹になる事案である。
とはいえ、かれも市村と田村の面倒をみつつ、いざとなったらちゃんと二人を護り抜くであろう。
しらんけど……。
五稜郭を出発してしばらくしてから、俊冬と俊春が握ってくれた玄米のおむすびを一個喰った。
なにせ割り当てが三個である。大切に喰わなければならない。
二股口まで軽快に進む。お馬さんたちの調子はよく、ときには、ときにはと調整しながら向かった。
あまり会話もなく、思ったよりもはやく到着した。
伝習隊の歩兵や衝鋒隊の兵士を呼びよせ、運んできた武器弾薬を協力して土塁胸壁を築いている場所へと運び込んだ。
「副長、物見にいってきます」
「ああ、頼む」
副長が俊冬の申しでを了承するまでには、の姿が消えていた。
ついでに相棒の姿も。は、広範囲で物見をおこなうのだろう。
ちっともじっとしやいない。
やはり俊冬や俊春は、マグロ体質なんだな。
動きを止めればソッコー死んでしまうのかもしれない。
それにしても、副長も俊冬も深夜になにもなかった、起こらなかったって感じでやりすごしている。
おたがいに、どう思っているのだろう。
凡人のおれには、心や表情をよんだりなんていう器用なことはできない。
つまり、二人がなにを思ったりかんがえたりしているかが、さっぱりわからない。
最初の敵との戦いで崩れた土塁胸壁や追加でそれを築くため、全員が一丸となって力仕事に精をだした。
天気の悪い日がつづいている。
そのため、地面がぬかるんでしまっている。
つるっと滑って転んだり、下まで滑り落ちてしまったりなんてことはしょっちゅうである。
みんな、軍服も身体やも泥だらけになってしまった。
各ポイントに配置し、武器弾薬の供給もそれぞれ完了した。
準備は整った。
あとは、敵軍の再来をまつばかりである。
手ぐすね引いてとは、まさしくこのことであろう。
一方、副長はあいかわらずである。泥だらけで作業をしているおれたちを、ムダにカッコつけたポーズで眺めている。
つまり、岩に片脚を置き、士官用のレインコートの裾を風にたなびかせているのである。
おいおい、あんたもすこしは手伝ったらどうだい?
そんなことは思うべきではない。
世紀末的にカッコいい男は、うんこをしないのと同様に泥にまみれてはいけないのだから。
そんな副長も、どことなく元気がないようである。