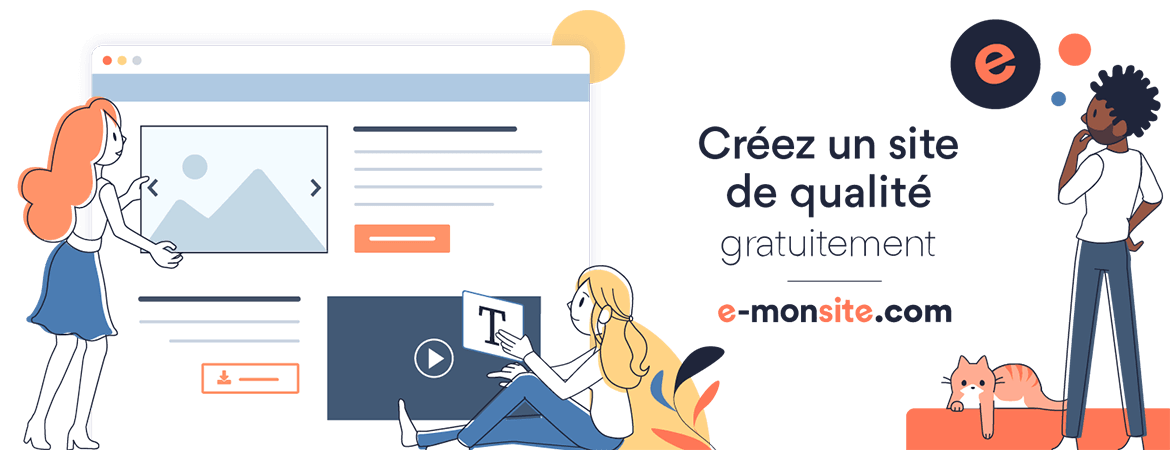『せや、外に友だちを作ればええ。話したいと思える人は居らへんの?』
それを聞いた桜花は、直ぐに花の姿を浮かべた。優しくて、芯が通った可愛らしい女子である。まさに愛嬌があるとは彼女のことを指すのではないか。
『…………い、居ます。清水寺さんの近くのお団子屋のだから…………』
『男やから、何おす。友だちになりたいと思った自分の勘を信じてみるんや。きっと、その秘密も全部受け入れてくれるかも知らんやろ?踏み出さな分からんことなんて、ようけある。……ほら、この壬生菜の浅漬け。子宮內膜增生 美味しゅう出来たから、これ手土産にして話し掛けといで──』 四半刻以上歩けば、すぐに目的地が見えてきた。店の前へ立つと、大きく深呼吸をする。
恐れを抱く自分の心を叱咤しながら、そっと暖簾を潜った。
「ご、ごめんください……」
そのように言えば、直ぐに花が顔を出す。桜花を見るなり、花が咲いたような笑みを浮かべて寄ってきた。
「桜花はん、おこしやす。また来てくだはって嬉しおす」
「あ、えっと……その……。こ、この前は御免なさい。これ……壬生菜の浅漬け……。美味しいから、是非召し上がって下さい…………」
あまりの眩しさにまともに目を合わせられず、下を向きながら壺を差し出す。
すると桜花の手ごと、柔らかで暖かい手が包んだ。
「おおきに。うち、壬生菜好きなんよ」
顔をあげれば、裏表のない透き通った笑顔が向けられる。それを見ていると、心の中の雲が少しずつ晴れていくような気にさせられた。
──やっぱり、この子と友だちになりたい。
「あ、あのっ、」
その時、暖簾を掻き分けて人が入ってきた。振り向けば、そこには洒落た着物を纏った男が立っている。
「あっ、アンタ、壬生狼の……!何やっけ……。せや、桜花はんや」
「弥八郎さん。ご無沙汰しています」
「……前は、いや前のようやなんて言うてしもうて」
わざわざそんなことを気にしていてくれたのかと、桜花は驚いたように弥八郎を見た。そして、目を細めて口角を上げる。
「いえ、謝らないで下さい。…………それが本当ですから」
そのように言えば、花と弥八郎は目を丸くして顔を見合わせる。前にもこのような場面があったな、と桜花は可笑しい気持ちになった。その反面で、気味悪がられたらどうしようと、恐れが湧く。
「ほ、本当て…………その、女子……てことか?」
気を使ってか、弥八郎は周囲を気にしつつ声を潜めた。
「…………はい」
もう後には引き返せないと、桜花は目を瞑る。
「…………か、」
そこへ黙っていた花が口を開いた。
「かっこええなぁ……!まるで"平家物語"の巴御前みたいや!」
「と……巴御前?」
思わぬ言葉に、桜花はキョトンとする。
「せや、知らへん?一人当千のやて言われとったらしいえ。うちを助けてくれた時の桜花はん、まさにそないな感じやった……。ええなぁ、ええなぁ。かっこええわぁ〜!」
まるで憧れを見るかのように、胸の前で両手を合わせて喜ぶ姿を見て、途端に力が抜けた心地になった。あれほど深刻に考えていたというのに、実際はこのようにもすんなり受け入れてもらえるとは思わなかったのだ。 茶屋からの帰り道に桜花は鴨川沿いを歩いていた。川沿いには等間隔に桜が咲き誇り、行き交う人々の目を楽しませる。そんな彼女の表情も明るく、心做しか頬も緩んでいた。
それは春の陽気に釣られたというよりも、先程の茶屋での出来事のせいである。あの後、勇気を振り絞って二人へ友達へなってくれないかと言ったところ、快諾されたのだ。
──言っちゃった、ついに言っちゃった。まさかあんなにあっさりと了承して貰えるなんて。もっと早く言えば良かった。
爽やかな風が道に面した店の暖簾を揺らす。気になる店はちらほらあるが、何たって先立つものを持ち合わせていなかった。冷やかすのは良くないと、春に誘われるまま歩みを進める。
気付けばその足は、吉田の住む長屋の近くへと向かっていた。
別に家を訪ねるのではなく、ただ川沿いを南下しているだけだと言い訳じみた言葉を胸の内に浮かべていると、左胸の痣がずくりと疼く。
──吉田さんが近くに居るんだ。
脳裏には優しげにこちらを見る吉田の顔が浮かび、自然と胸が高鳴り出した。ふわりと甘い香りが鼻腔を掠める。それが