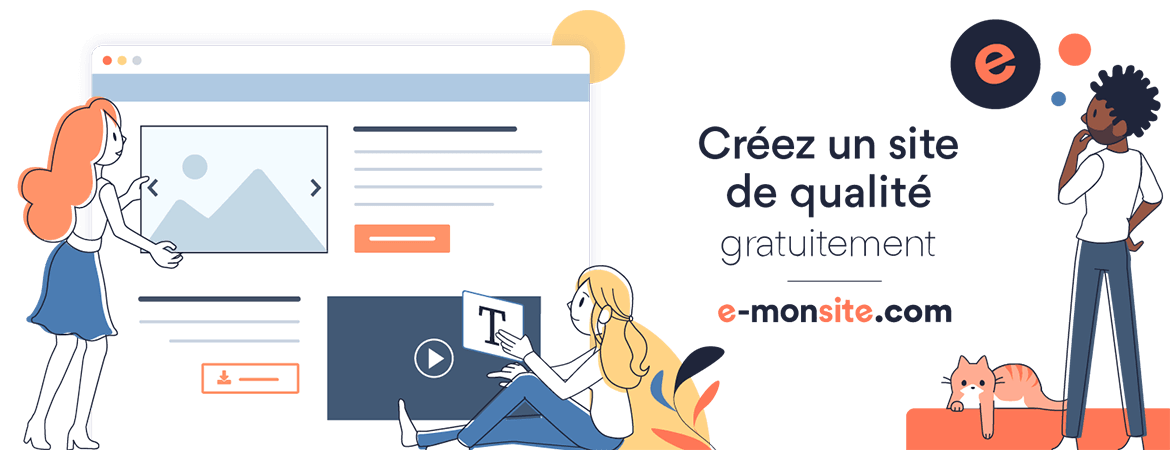「人と交わることのない山奥で育ったがゆえに、そういった知識や経験が無いのでしょう。共に暮らせば、人としての物言いはすぐに覚えられましょう」
梅ノ井と老臣を見つめ微笑んだ。
イダテンは、姫の口にした言葉に困惑した――単に物の例えか。あるいは深く考えずに出た言葉か。
梅ノ井も、呆けたように姫を見ていた。
姫の言葉が理解できなかったのだろう。
聞き間違えたと思っているのかもしれない。
老臣一人が、姫の言葉に頬を緩めた。
姫は、それよりも、と、やわらかに続けた。
「黒がとてもよく似合いますよ。冬に備えた衣も用意させましょう。殺生をしなくても良いように」
イダテンが打ち掛けていた熊や鹿の毛皮のことを話しているのだとわかった。
「出来ぬ」
即座に答えた。
自分でも驚くほどの強い調子だった。脫髮 維他命
姫は、悲しげに眉根を下げた。
「殺生をしなければならない理由があるのですか」
「話してもわかるまい」切り捨てるような物言いに女房は絶句し、老臣は、怒気をはらんだ鋭い目つきで太刀に手を伸ばした。
イダテンは身動ぎひとつせず、老臣の目を見返した。
動けなかったのではない。
言葉で伝えることをあきらめたのだ。
怖ろしくはなかった。
もはや守るべきおばばもいない。
死んで泣く者もいない。
生まれも育ちも違う者同士がいくら話したところで、わかりあえぬのだ。
ゆえに、言葉を飲み込んだのだ。
――おれの殺生は食うため、生きるためだ。
武士のように領地を奪いあうためではない。
先に住んでいた者から土地を取り上げ、収穫を取り上げ、餓死させるためではない。
坊主や、この地の領主どもがなにをしているか、知っておるか?
百姓に銭を貸し、返せねば借金のかたに下人とし、次は、その下人を売り買いする。
そのような坊主の説く、衆生の救いとやらを信じられるか?
領地や利を守るため僧兵だけでは足らず「死こそ救済」と民百姓を煽る坊主の言い草を信じろと言うか?
その領主や坊主の上に立ち、このような豪奢な邸に住み、着飾って暮らしている者に話したところで何になる。「じい!」
制止する姫の声が聞こえた。
だが、姫が止めなくても忠信は太刀を抜かな
かっただろう。
イダテンの目を見たからだ。
これほど暗い目をした小童を見たことがない。
生に執着しなくなった者の目だ。
不憫なことだ。
わずか十歳にしてこの世に絶望している。
あれはまだ、忠信が御衣尾にある六地蔵に供え物をしていた二年ほど前のことだ。
兼親の郎党と思われる男が崖から落ちて命を落とした。
忠信が追い込んだのだ。
その男が直前にイダテンに矢を射かけていたからだ。
あの時、イダテンはいともたやすくよけた。
ところが、こたび、こやつはあっさりと倒されていた。
しかも、姫の牛車の前で、だ。
衣が濡れ、熱を出していたのは確かだったが、イダテンを痛めつけていた男達のことを調べさせた。
武辺者と言われる忠信とて、それぐらいの頭は回る。
兼親たちとつながっていたことが分かった。
イダテンを潜り込ませるための策ではないかと疑った。
イダテンが自分の意志で姫や主人の命を奪いに来るとは思わなかったが、おばばが質に取られていたら話は別だ。
そう考えたからだ。
だが、いらぬ心配だったようだ。
少なくとも人の命を奪おうとする者の目ではない。忠信は柄から手を離したが、梅ノ井の興奮はおさまらなかった。
「なっ、なんという無礼なもの言い! 忠信殿、このような者を許しておいて良いのですか?」
「梅ノ井殿」
忠信は、梅ノ井のかん高い声にうんざりしながらも感情を押し隠した。
もともと世の習いにうるさい、このおなごとは性が合わぬのだ。
「梅ノ井殿の言われるように、恩人である姫様にとる態度ではない――わしとてそう思いますぞ。とはいえ、梅ノ井殿も知ってのとおり、イダテンは、その力、この世に並ぶものなしと言われたシバの子じゃ。